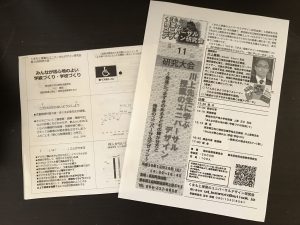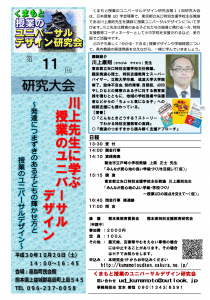新年明けましておめでとうございます。昨年も本研究会では、全国的にも有名な講師の方々をお招きしての講演会や、地元で様々な実践を重ねておられる先生と共に学ぶ学習会などを企画してきました。どの会も毎回多くの方々にご参加頂き大盛況でした。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。今年も本研究会では、どの子も楽しく・分かる・できる授業のユニバーサルデザインをたくさんの先生方々と共に学んでいければと思います。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて早速、第21回の拡大学習会のお知らせです。
くまもと授業のユニバーサルデザイン研究会第21回目の学習会は、鶴﨑泰文先生(熊本市教育センター) と山田光太郎先生(熊本市立日吉小学校)による算数の公開授業と授業研究会を、長嶺小学校で行います。鶴﨑先生の公開授業では、算数そのものの教科や授業の考え方について、山田先生の公開授業では授業UDの視点での算数の授業作りについて、実際の授業や子どもたちの姿を見て考えていきます。多数のご参加をお待ちしています。

期日:平成31年2月23日(土) 8:30〜12:30(受付は8:30〜9:00です。)
会場:熊本市立長嶺小学校
会の流れ:
8:30 受付(児童昇降口)
9:00 公開授業1:「 算数(3年生)」授業者:山田光太郎先生(熊本市立日吉小学校教諭)
10:00 公開授業2:「算数(3年生)」授業者:鶴﨑泰文先生(熊本市教育センター)
11:00 授業解説および授業研究会
12:00 まとめ:菊池哲平先生(熊本大学大学院教育学研究科准教授)
12:25 諸連絡
12:30 閉会
参加費:1000円
申し込み:申し込み用サイト(こくちーず)↓からお願いします。
https://www.kokuchpro.com/event/97aa10b6d1be22f9e3787ff995afdd2b/
チラシのダウンロード(PDF)↓
問い合わせ :くまもと授業のユニバーサルデザイン研究会
事務局担当:ud_kumamoto@outlook.jp
宮本 美哉 090(1343)8591